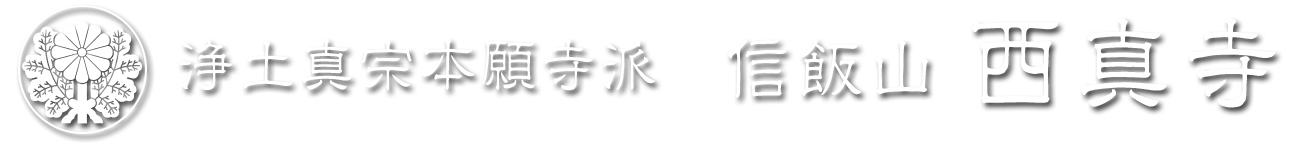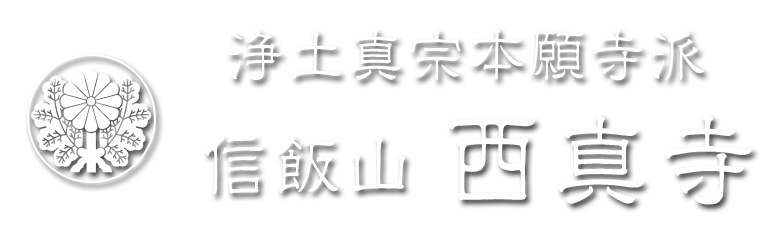法事(法会)とは、一般的に身内などの家族や親戚が集まって、「故人の冥福を祈り」、その霊を慰める仏教的な儀式をいい、追善供養を指しています。
しかし、お釈迦様は霊の存在を弟子に聞かれても、答えていません(無記)。その上で無用な論争は、苦しみからの解放という目的に対し意味を持たないと答えました。霊とは、人の恐れや迷い、苦しみから生じる、つまり煩悩が引き起こす現象だとして、煩悩の原因が我執(渇愛:自己愛)によるもの、その為の救済を説いたのです。
また冥福とは、「冥土の幸せを願う」という意味で、冥土とは死者の霊魂が行く暗黒の世界を指し、地獄・餓鬼・畜生の三悪道を意味します。故人の冥福を祈る行為とは、「死んだら暗黒世界である地獄・餓鬼・畜生に堕ちるだろうけど、何とか幸せになってね」であり、これが追善供養の意味です。そして菩提寺とは菩提=「死後の冥福」ですから、死後の冥福を弔う(他人に同情をかける:上から下に恵みをたれる)寺という意味に成ります。
この為、追善供養として法事を捉えていない浄土真宗のお寺は、菩提寺とは言わず、同情はせずに共感する立場、つまり他者の体験する苦しみを自分の事として汲み取る姿勢を持つ為、上下関係は存在せず「所属寺」や「手次寺」と言います。
この傾聴の姿勢がもたらす理論は、現代における臨床理論で科学的に実証されています。
カウンセリングや心理療法における、カウンセラー(聴き手)は、クライアント(話し手)との対等性を維持します。何故ならば、苦しみを傾聴し、共感する立場のカウンセラーが上位に立つと、クライアントが本来持つ自己治癒力が活性化しないことが立証されているからです。尚、対等性とは馴れ合いではなく、お互いが尊重し合える関係性、つまり浄土真宗の、御同行、御同朋の精神性に基づいているのです。
もし皆さんが亡くなったら、救済原理の無い冥土での幸せを祈られたいと思いますか?これが愛別離苦(愛する人と別れなければならない苦しみ)を抱えた家族や親戚が、上位から亡き人に対し言うべき言葉とは、とても言い難いと思います。死んだら暗闇の世界に落ちてお終いならば、虚しさだけが残り、享楽主義(生きているうちに欲望の全てを満たす考え)に走る事に成るでしょう。
浄土真宗では、故人は阿弥陀仏の本願力によって救われ、お浄土に往生して仏さまに成るのです。我々が亡き人に対し上からの立場で冥福を弔い、かつ祈る必要はありません。また、故人の死を通して、阿弥陀仏の教えに会う仏縁に感謝するのが法会(仏の教えに会う)、つまり法事であります。
法事とは、私たちが、故人の冥福を祈り、霊を慰めるのではなく、身を持って死を私たちに教えてくれた故人から、様々な問いと願いが掛けられていることに気付き、自己を振り返り、それに応えていく人生の節目を創造する歩みの事なのです。